はじめに
私は以前、日産自動車の開発職として働いていたんだ。特にEV(電気自動車)用バッテリーに関する研究開発を担当していた。この記事では、開発職の仕事内容、働いて感じたこと、そして日産自動車の業績低迷の背景について、客観的な視点と主観的な意見の両方を交えながら話していこうと思う。
この記事の目次(クリックでジャンプ可能)
EVバッテリー開発の仕事内容

EVバッテリーの開発といっても、やることは本当に多岐にわたるんだ。主に以下のような業務を担当していた。
- セルの選定と評価
EVバッテリーは「セル」と呼ばれる小さな電池が集まって構成されている。どのメーカーのセルを採用するか、どの仕様が最適かを検討し、試験を行うんだ。 - バッテリーパックの設計
セルをどのように配置し、どのように冷却するかを考えながら、最適なバッテリーパックを設計する。安全性や耐久性も重要なポイントになってくる。 - ソフトウェアと制御の開発
バッテリーの充放電を最適に管理するためのソフトウェア開発も重要な業務の一つだ。バッテリーの寿命を延ばし、安全性を確保するために、制御技術が欠かせない。 - テストと評価
バッテリーの性能を確かめるために、耐久試験や衝撃試験を行う。実際の走行環境を想定したテストを繰り返し、問題がないか確認するんだ。 - コスト管理と量産化
いくら高性能なバッテリーでも、コストが高すぎると市場に受け入れられない。そのため、量産化を考えながらコストを抑える工夫も求められる。
実際に働いて感じたこと

良かった点
- 技術の最前線で仕事ができる
EVは自動車業界の未来を担う分野であり、その開発に携われることは非常にやりがいがあったんだ。 - チームワークが求められる環境
バッテリー開発は一人ではできるものではなく、電気、化学、機械、ソフトウェアなど多くの分野のエンジニアと協力しながら進めていく必要がある。異なる専門知識を持つ人と協力しながら仕事を進めるのは刺激的だったよ。 - 環境問題への貢献
ガソリン車からEVへの移行は、環境負荷を低減する大きなステップだ。自分の仕事が社会貢献につながっていると感じられるのは大きなモチベーションになった。
大変だった点
- 開発スケジュールが厳しい
自動車業界は競争が激しく、特にEV分野ではテスラや中国メーカーとの競争が熾烈だ。短期間で高品質なバッテリーを開発することが求められ、プレッシャーが大きかった。 - コストと性能のバランスの難しさ
高性能なバッテリーを作ることは簡単ではない。コストを抑えながら性能を向上させるのは、非常に難しい課題だった。 - 社内の意思決定プロセスが遅い
伝統的な大企業ならではの問題として、新しい技術を導入する際の意思決定が遅いと感じることがあった。特に、ライバル企業がどんどん新しい技術を投入する中で、スピード感の遅さがもどかしかったよ。
日産自動車の業績低迷の背景
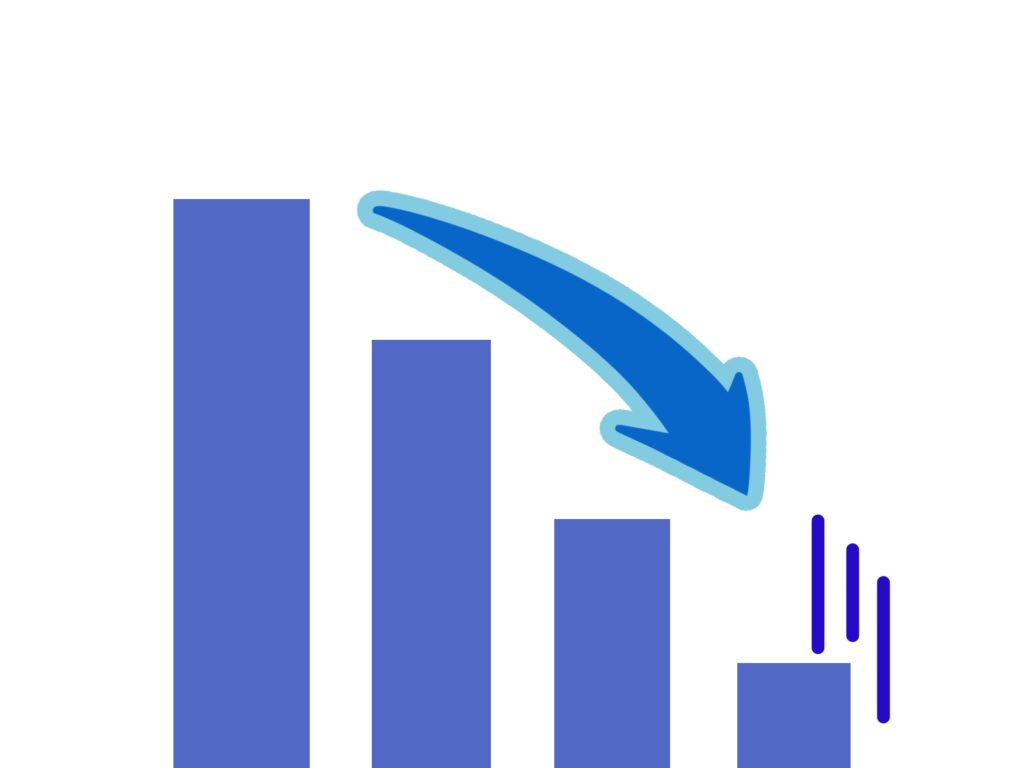
最近、日産自動車の業績は低迷している。その理由について、客観的な視点と主観的な意見を交えて話していく。
客観的な視点

- 競争の激化
テスラやBYDなどのEVメーカーが急成長し、日産自動車はEV市場でのポジションを失いつつある。ついでに電気自動車が欲しい層に一通りいきわたったため、今後の需要は限定的と予想される。まだまだガソリン車、ハイブリッド車の競争が激しいんだ。 - 経営の混乱
ゴーン元会長の事件以降、経営体制が不安定になり、戦略が一貫しない状況が続いている。責任は経営陣にあるが経営陣は責任を取らず、過去と同じリストラで今回の業績悪化を乗り切ろうとしている。リストラするなら経営陣も総辞職するのが良いのではないか。何を考えているかよくわからないのが現状。 - ブランド力の低下
かつては日産自動車の車も売れていたが、最近はトヨタやホンダと比べてブランドの魅力が低下し値引きしないと売れない車になっている。 - 投資の遅れ
他のメーカーがガソリン車に投資するなか、消極的にEVに投資し、全ての自動車分野で某N自動車は出遅れてしまった。結果はすでに出ており、EVの販売は中国など一部を除いて、予想を大きく下回る状況で一人だけ負けてしまっている。 - ホンダとの関係悪化
ルノーとの関係よりも、ホンダとの交渉決裂による関係悪化のほうが今後の経営に影響を与える可能性が高い。業界内での提携は重要であり、この交渉失敗が今後の戦略にどのような影響を及ぼすのか注視する必要がある。
主観的な意見
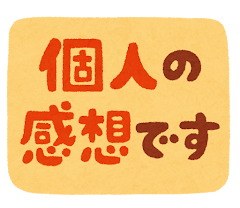
- 現場のエンジニアは優秀
実際に働いてみて感じたのは、エンジニア一人ひとりの技術力は非常に高いということ。ただ、管理職、経営層の影響で組織としての意思決定が遅いため、新しい技術を市場に出すのに時間がかかってしまう。社内政治に得意な人が多く、事業戦略を考えることができない責任者が多い。 - 巻き返しは不透明
ホンダとの提携交渉の失敗や、新しいモデルの投入がいつになるかなど、回復の兆しはまだ見えない。経営陣が変わらなければ仕事の質や経営戦略も大きくは変わらないだろう。今のところ経営陣がすべて刷新される様子はないので、しばらく低迷が続くと予想している。一消費者の視点からも日産の車を買う理由が見つからない。 - 内向的な仕事
基本的に社内を向いて仕事をしている。部長、役員の意向に沿って仕事をしている結果お客様の方を向いている人がいなくなってしまった。責任者がお客様の事を考えてものづくりをしていれば、もう少し良い結果になっていたかもしれない。
まとめ

日産自動車のEVバッテリー開発職として働いた経験を通じて、最先端の技術に携わるやりがいや、開発の難しさを実感した。また、日産自動車の業績低迷にはさまざまな要因があるが、組織の意思決定のスピードが上がらない限り、競争力を取り戻すのは難しいかもしれない。
まだまだガソリン車、ハイブリッド車の時代であることが改めて分かった。EVシフトが加速していくわけない。日産自動車が業界のリーダーとして復活するには、経営の抜本的な改革が求められるだろう。




コメント